ノンフライヤーを購入しようと考えているけれど、「後悔したくない」「自分に合っているか不安」と思う方も多いのではないでしょうか?
特に、ノンフライヤーの仕上がりや使い勝手、サイズ感など、購入後に気づくポイントが心配ですよね。
私はCOSORIのノンフライヤーを使用していますが、購入する前は、口コミを何度も確認して悩んだ経験があります!
の記事では、ノンフライヤーを実際に使用して感じたメリット・デメリットを詳しく解説し、購入の判断材料になる情報をお届けします。
ノンフライヤーで後悔したくない!という方は下記の商品を参考にしてみてください♪
→【後悔させない!】おすすめのノンフライヤー3選!!
この記事を読むと分かること
- ノンフライヤーを後悔する理由とその解決策
- ノンフライヤーが向いている人と向かない人の特徴
- サイズや機能の選び方など、後悔しない購入のポイント
- 実際のメリット・デメリットを徹底解説
- ノンフライヤーを最大限活用するコツ
これからノンフライヤーの購入を検討している方にとって、後悔を防ぎ、満足度を高めるための情報が詰まった内容となっています。ぜひ最後まで読んでみてください!
ノンフライヤーを後悔する理由とは?

後悔する理由①:調理の仕上がりが期待外れ
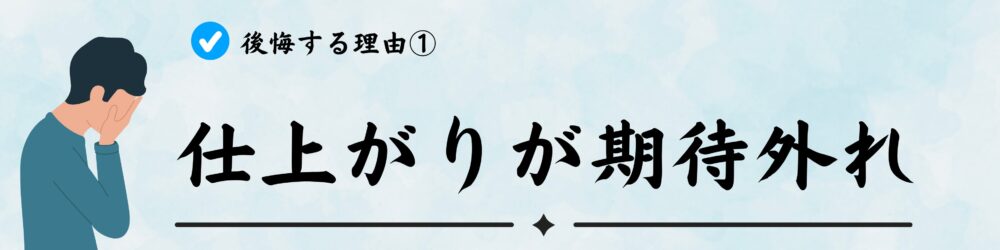
私がCOSORIのノンフライヤーを初めて使ったとき、一番気になったのが「揚げ物の仕上がりがどれくらい本格的になるのか?」という点でした。
正直、最初は揚げ物の代わりになると思い込んでいたので、食感や香りに少し違和感を感じたのも事実です。
ただ、これは使い方や期待値の調整で十分に解決できる問題だと気づきました。
揚げ物特有の食感が足りない?
ノンフライヤーの調理方法は「熱風を循環させて焼き上げる」仕組みなので、油で揚げたときのような衣のサクサク感やジューシーさがやや弱いことがあります。
特に冷凍ポテトや唐揚げを調理する際、「もう少しパリッとさせたい」と感じることがありました。
解決策としては、以下の方法が効果的です。
- 薄く油をスプレーする
COSORIのノンフライヤーは油を全く使わなくても調理可能ですが、仕上がりをより揚げ物らしくしたいなら調理前に食材へ軽く油を吹きかけると良いです。これだけで、衣のサクサク感が少し増します。 - 温度と時間を工夫する
説明書どおりの温度・時間設定でも問題ありませんが、食材によっては少し高めの温度で仕上げの数分を延長すると理想の仕上がりに近づけられます。
●期待と現実のギャップ
ノンフライヤーは「揚げ物を完全再現するもの」ではなく、ヘルシーかつ手軽に調理するための家電です。この認識のズレが後悔につながる原因の一つです。
- 目的を明確にする
ノンフライヤーは油を使わない分ヘルシーな仕上がりになりますが、揚げ物と同じものを求めすぎるとギャップを感じます。健康志向や時短調理を目指している人には最適です。 - 活用方法を工夫する
揚げ物だけでなく、焼き魚や野菜のロースト、パンの温め直しなど、多用途に使える点に注目すると「買ってよかった!」と思える瞬間が増えます。
ノンフライヤーの仕上がりは揚げ物と完全に同じではないものの、ヘルシーさと調理の手軽さで十分に満足できる家電です。
特に、少しの工夫で仕上がりのクオリティを上げられる点は魅力的です!
COSORIを使っている私も、最初は期待しすぎて後悔しかけましたが、今ではなくてはならない調理家電の一つになっています。
後悔する理由②:サイズが大きくキッチンで邪魔になる
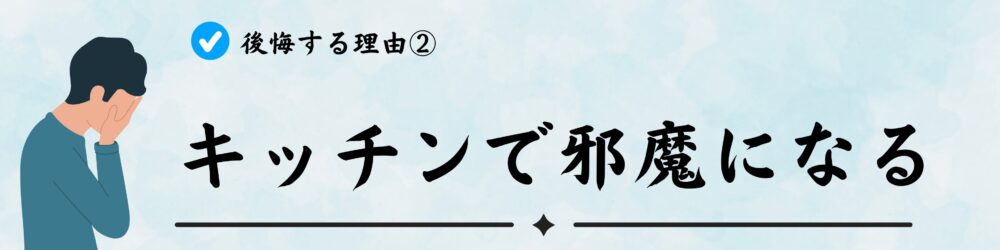
ノンフライヤーを購入して一番最初に気になったのが、そのサイズ感です。
特にCOSORIのように家族向けの大容量モデルを選ぶと、コンパクトなキッチンでは少し圧迫感を感じることがあります。
具体的なサイズ感の問題点
- 調理スペースを取られる
COSORIのノンフライヤーは奥行きがあるため、調理台やキッチンのカウンターに置くとスペースをかなり消費します。特に調理を並行して行う際、置き場所が狭く感じることがあります。 - 収納場所に困る
サイズが大きいと、使用しないときにどこにしまうかが悩みどころになります。特に賃貸などで収納スペースが限られている場合、頻繁に使わないなら邪魔に感じることも。 - 移動が面倒
ノンフライヤー自体の重量がそこそこあるため、「使うたびに出し入れする」スタイルだとだんだん億劫になりがちです。
解決策とアイデア
- 設置場所を工夫する
キッチンカウンターの一角や棚の上など、動線を邪魔しない場所に設置するのがおすすめです。また、使う頻度が高い場合は、常設スペースを確保する方が快適に使えます。 - 小型モデルを検討する
COSORIにも一人暮らし用のコンパクトモデルがあるので、大型が必要ない場合はそちらを選ぶのも一つの手です。 - 家電収納ラックを活用する
最近はノンフライヤー専用ラックなども販売されており、縦のスペースを活用して効率的に収納できる工夫がされています。
サイズの大きさは確かに気になるポイントですが、設置場所を工夫するだけで問題が解消します。
私も最初は邪魔に感じましたが、家電収納ラックを使ってキッチンを整理したことでむしろ見た目もスッキリしました。
大容量の調理ができるメリットを考えれば、多少のスペースは十分に許容範囲だと思います!
後悔する理由③:清掃が面倒で続かない
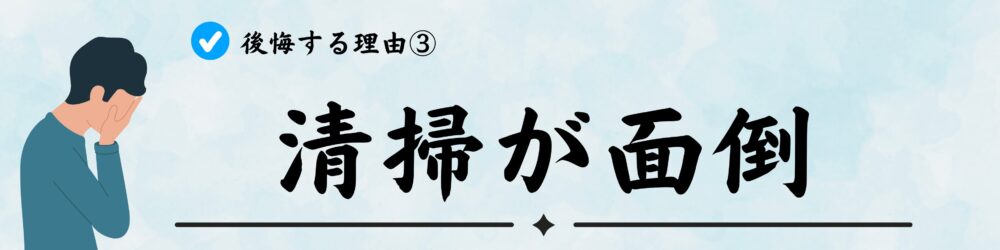
ノンフライヤーを使う中で意外と気になるのが「清掃の手間」です。
私がCOSORIのノンフライヤーを購入して最初に感じたのも、調理後に出る油汚れや食材カスをどうきれいにするかでした。
これを上手に対処しないと、「使うのは楽だけど、後片付けが大変!」と感じる原因になります。
ただし、いくつかの工夫で驚くほど楽にできることに気づきました。
清掃が面倒に感じる理由
- 油分やカスのこびりつき
揚げ物や肉料理を作ると、食材から出た油や汁がトレイに溜まります。この汚れは時間が経つと乾燥し、落としにくくなるのが面倒だと感じる原因です。 - パーツが多い
COSORIはカゴとトレイが取り外せる設計ですが、分解して洗う必要があるため、清掃の手間が増えたように感じることも。 - 細かい部分の汚れ
トレイの網目やカゴの角など、細かい汚れが溜まりやすい部分の掃除が少し厄介です。スポンジでは届きにくい箇所もあるので、慣れるまでは大変かもしれません。
清掃を楽にするポイント
- 調理前にクッキングシートを敷く
トレイの上にクッキングシートや専用の耐熱シートを敷くだけで、汚れをほぼ防げます。調理後にシートを捨てるだけなので手間が激減します。 - 専用ブラシを使う
細かい部分の掃除には、100円ショップで買える小型のブラシを使うと効率的です。私はブラシを導入してから清掃のストレスが減りました。 - 食洗機を活用する
COSORIのパーツは食洗機対応なので、忙しい日や週末のまとめ洗いには食洗機を使うことで手間を省けます。
清掃が面倒に感じるのは最初のうちだけで、工夫次第で驚くほど楽になります。
私も最初は清掃の手間に戸惑いましたが、今では清掃を含めても手軽に感じています。
調理後の片付けもストレスなくできるようになれば、ノンフライヤーの便利さをもっと実感できます!
後悔する理由④:値段に見合った満足感が得られない場合がある
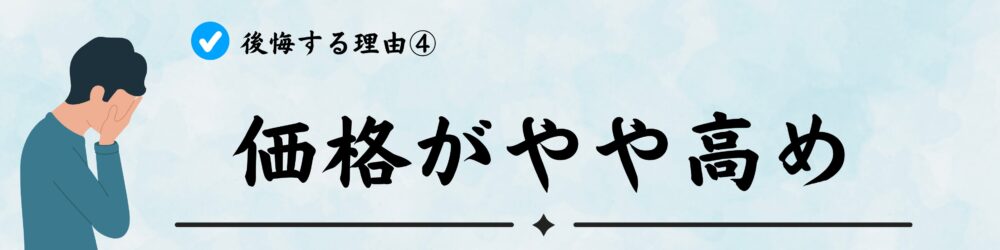
COSORIのノンフライヤーは性能やデザインが優れている分、価格がやや高めです。
購入を迷う理由として、「値段に見合った価値があるのか?」という点は誰もが気になるところです。
私も購入前に価格については悩みましたが、使い方を工夫することで十分満足できる結果になりました。
値段に見合わないと感じるケース
- 使用頻度が低い場合
ノンフライヤーをあまり使わない家庭では、価格に対するコスパが悪く感じることがあります。特に、「揚げ物を作る頻度が少ない」という場合は他の家電で代用できるのでは?と考えることも。 - 期待値が高すぎた場合
ノンフライヤーを「揚げ物そのものを完全再現するもの」と期待すると、仕上がりに物足りなさを感じるかもしれません。ただ、揚げ物以外の使い方もできると理解すれば後悔しにくいです。 - 価格の比較をしない場合
Amazonや楽天などで販売されているノンフライヤーにはさまざまな価格帯のモデルがあります。同じ性能でもより安価なモデルを選べる場合があるので、購入前の比較が重要です。
満足感を得るための工夫
- 活用方法を広げる
揚げ物だけでなく、焼き魚や野菜のロースト、さらにはパンの温め直しなどに使えば、1台で多くの料理に対応できます。これにより、「高価な家電を買った価値がある」と実感しやすいです。 - 健康面での効果を考える
油を使わないことで、摂取カロリーを大幅にカットできる点は大きな魅力です。私はこの効果を実感してから、健康的な食生活を補助する家電として価値を感じるようになりました。 - 家族全員で使えるレシピを探す
家族で楽しめるレシピを見つけると、自然と使用頻度が増え、満足感も向上します。COSORIのレシピブックには実用的なアイデアがたくさん載っていて参考になります。
ノンフライヤーの価格は高く感じるかもしれませんが、健康志向や料理の手軽さを考えると十分に元が取れる家電です。
COSORIを使い始めてから、ヘルシーな料理を簡単に作れる点に満足しています!
後悔する理由⑤:料理の幅が思ったほど広がらない
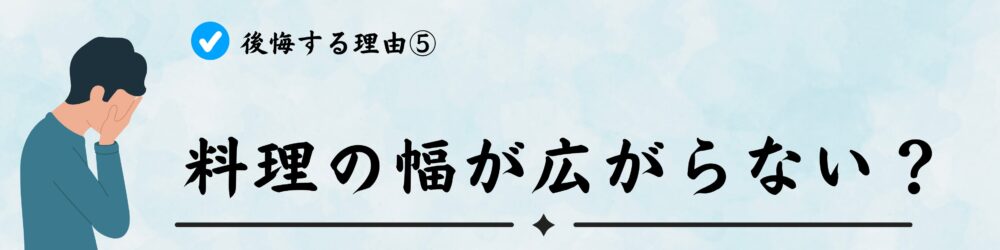
ノンフライヤーに期待するのは「これで料理のレパートリーが増える!」という点だと思います。
ただ、最初は揚げ物メインで考えがちなので、使い方に工夫がないと「意外と作れるものが限られている?」と感じてしまうこともあるかもしれません。
料理の幅が広がらない理由
- 揚げ物専用というイメージ
ノンフライヤーは揚げ物が得意な家電ですが、揚げ物以外の使い方に気づけないと、料理の幅が狭く感じられます。 - 初期のレシピ不足
初めて使うときに何を作ればいいのか迷うと、「結局いつも同じ料理」となりがちです。(笑) - 温度設定や時間調整のコツが必要
調理に慣れるまでは失敗することもあり、料理の幅が狭いと感じることがあります。
料理の幅を広げる工夫
- 多用途に挑戦する
揚げ物だけでなく、ローストビーフ、焼き野菜、グラタン、さらにはスイーツまで作れるので、幅広いレシピを試してみると楽しいです。 - 専用レシピを活用する
先ほども言いましたがCOSORIには専用レシピブックが付属しており、新しいアイデアが満載です。また、SNSやブログなどで他のユーザーのレシピを探すのもおすすめです。
ノンフライヤーは使い方次第で料理の幅を広げることができます。
私も最初は揚げ物だけを作っていましたが、いろいろ試すことでレパートリーが増え、今ではなくてはならない家電になっています!
購入前に知るべき注意点
ノンフライヤーを購入する前に知っておくべきポイントを押さえておけば、後悔を防ぎやすくなります。
以下は、COSORIのノンフライヤーを使っている私が感じた注意点です。
購入前の確認ポイント
- サイズ感を確認する
COSORIはサイズが大きめなので、キッチンや収納スペースに余裕があるか事前にチェックすることが大切です。 - 用途に合っているか
揚げ物がメインの家電なので、普段から揚げ物や焼き物を作る機会が多い人に向いています。 - 価格と性能のバランス
同価格帯の他の家電と比較して、どの性能が必要かを考えることも重要です。 - 健康志向に合っているか
油を使わない調理はヘルシーですが、揚げ物そのものの再現を求めすぎないことがポイントです。
購入前にしっかりと用途や条件を確認すれば、満足感の高い選択ができます。
COSORIは多用途で使いやすく、特に健康志向の方にはおすすめです!
ノンフライヤーで後悔しないための選び方

目的別に適したモデルを選ぶ
ノンフライヤーを選ぶ際、どのような目的で使用するかを明確にすることが大切です。
私がCOSORIを選んだのも、家族みんなで楽しめる料理を作りたいという目的があったからです。
しかし、この目的があいまいだと、使わなくなる原因になります。
目的別の選び方
- 揚げ物を頻繁に作りたい場合
揚げ物がメインの目的なら、熱風の循環効率が良く、ムラなく調理できるモデルを選びましょう。COSORIのように油を使わずにサクサク仕上げができるタイプがおすすめです。 - 多用途に使いたい場合
焼き物やロースト、さらには温め直しまで幅広く使いたいなら、温度調整機能や多段式のトレイがあるモデルを選ぶと便利です。 - 一人暮らしや少人数向け
一人暮らしなら容量の小さいモデルがおすすめです。COSORIにもコンパクトサイズがあり、キッチンスペースを有効活用できます。 - 健康志向の食生活を目指す場合
油をカットしたヘルシー料理が目的なら、ノンフライヤー全般が向いています。ただし、食材ごとの調理時間を細かく設定できるモデルを選ぶとより便利です。
ノンフライヤーは目的に合ったモデルを選ぶことで、満足度が大きく変わります。
まずは自分や家族の生活スタイルに合った用途を明確にし、それに応じた機能を持つモデルを選びましょう!
容量は家族の人数に合っているか?

ノンフライヤーを選ぶときに意外と重要なのが容量です。
私がCOSORIを選んだ理由の一つも、この容量の大きさでした。
家族で使う場合は、容量が足りないと複数回に分けて調理する必要があり、面倒だと感じることもあります。
容量選びの目安
- 一人暮らしの場合
2〜3リットル程度のコンパクトなモデルがおすすめです。一度に調理できる量が少なくても、自分一人分であれば十分対応できます。 - 2〜3人の家庭の場合
4〜5リットル程度の中型モデルが便利です。例えば、唐揚げなら10個以上が一度に調理できるので、食事の準備がスムーズです。 - 4人以上の家庭の場合
6リットル以上の大容量モデルがおすすめです。COSORIはこのカテゴリに入るモデルが多く、一度にたくさんの料理を作れるので、特にファミリー向けとして人気があります。
注意点
- 容量が大きいと本体サイズも大きくなるため、キッチンのスペースを事前に確認しておくことが重要です。
- 大きすぎるモデルを選ぶと、少量の調理では熱風が効率よく循環せず、仕上がりがムラになることがあります。
容量は使い勝手に直結する重要なポイントです。
家族の人数や調理頻度に合わせて適切なサイズを選ぶことで、より快適に使えます。COSORIの大容量モデルは、ファミリー層には特におすすめですよ!
設置場所の確保とサイズの確認

ノンフライヤーを購入する前に必ず確認すべきなのが設置スペースです。
私がCOSORIを使い始めたときも、キッチンのスペースをしっかり確保しておいて正解でした。
サイズ感を事前に確認しておかないと、「置く場所がない!」という後悔に繋がりやすいです。
設置場所で確認すべきポイント
- 本体サイズ
COSORIの大容量モデルは奥行きがあるため、調理台の幅や奥行きを事前に測定しておくことが大切です。 - 熱風が出る方向
ノンフライヤーは調理中に熱風が排出されるので、周囲に十分なスペースを確保する必要があります。特に壁や他の家電との距離には注意しましょう。 - 重量
大型モデルは重さがあるため、使うたびに移動するのは大変です。使用頻度が高い場合は、常設できるスペースを確保するのがおすすめです。
設置場所を事前にしっかりと確認することで、購入後の後悔を防げます。
COSORIのモデルは少し大きめですが、それを補って余りある便利さがあるので、スペースを確保してからぜひ試してみてください!
必要な機能を見極める(温度調整やタイマー機能など)

ノンフライヤーを選ぶときは、どんな機能が必要かを見極めることが重要です。
COSORIのノンフライヤーは多機能ですが、必要ない機能が多すぎると逆に操作が面倒になることもあります。
必要な機能一覧
- 温度調整機能
幅広い温度設定ができるモデルは、揚げ物以外の調理にも対応できます。COSORIは80℃〜200℃まで調整可能なので、焼き物からデザートまで作れます。 - タイマー機能
調理時間をセットできるタイマー機能は、放置調理に便利です。終了時に自動で電源が切れるので安心感もあります。 - プリセットメニュー
COSORIにはプリセットメニューが搭載されており、唐揚げやポテトなどよく作る料理をワンタッチで設定できます。 - 分解して洗える構造
清掃がしやすい設計かどうかも重要なポイントです。
必要な機能を明確にすることで、使いやすいモデルを選べます。
COSORIは多機能ながらシンプルな操作性が魅力で、初心者にもおすすめです!
ブランドごとの特徴を比較
ノンフライヤーはさまざまなブランドから販売されていますが、それぞれに特徴があるため、購入前に比較しておくことが大切です。
私がCOSORIを選んだのも、ブランドの特徴を調べた結果、自分のニーズに最も合っていると感じたからです。
主なブランドの特徴比較
COSORI
- 特徴: 高性能で多機能、サイズもミニサイズから大容量モデルまで豊富に揃っている。
- おすすめポイント: プリセットメニューが豊富で初心者にも使いやすい設計。アフターサポートがしっかりしている点も安心材料です。(2年保証あり)
Philips(フィリップス)
- 特徴: ノンフライヤーのパイオニア的存在で信頼性が高い。独自の「ラピッドエア技術」による熱風循環が魅力。
- おすすめポイント: ブランド力が強く、揚げ物のクオリティが高いモデルが多い。
ブランドごとの特徴を比較することで、自分のライフスタイルや予算に合った製品を選べます。
私は、品質と使いやすさのバランスが良いCOSORIを選んで大正解でした!
実際の口コミや評判を確認する

ノンフライヤーを購入する際、実際に使用した人の口コミや評判を確認するのは非常に重要です。
私も購入前に多くのレビューをチェックし、メリットとデメリットを把握してから決めました。
口コミで注目すべきポイント
- 調理の仕上がりに関する声
「揚げ物の仕上がりはどうか」「ヘルシーに仕上がるか」など、実際の仕上がりに関する口コミは購入の参考になります。 - 使いやすさ
「操作が簡単か」「メンテナンスがしやすいか」など、日常使いのしやすさに関する評価を確認しましょう。 - 耐久性
「何年使えるのか」「壊れにくいか」という口コミは、長期的に使えるかどうかを判断する材料になります。 - サポート対応
万が一不具合があった際の保証やカスタマーサポートの対応についての意見も重要です。
COSORIの口コミを調べた結果
- 良い口コミ
「揚げ物以外にもいろいろ作れる」「操作がシンプルでわかりやすい」「家族全員分を一度に作れて便利」といった声が多く、ファミリー層からの評価が高いです。 - 悪い口コミ
「サイズが大きく置き場所に困る」「清掃がやや面倒」という意見もありますが、設置場所の工夫や清掃用の道具を揃えることで対処可能です。
口コミを確認することで、実際の使い勝手や注意点を知ることができます。
私も購入前に多くのレビューを参考にし、メリットとデメリットを理解してからCOSORIを選びました。結果、満足度の高い買い物になりました!
価格帯の目安とコスパの良いモデルを選ぶ
ノンフライヤーを選ぶ際、価格帯の目安を把握しておくことも重要です。
COSORIのように高機能なモデルは少し高価ですが、その分得られるメリットも大きいです。
価格帯の分類
- 1万円以下のモデル
- 特徴: コンパクトでシンプルな機能のみ。揚げ物がメインの用途に限定されることが多い。
- おすすめ対象: 初めてノンフライヤーを試してみたい人向け。
- 1万〜2万円のモデル
- 特徴: 温度調整やタイマー機能など、多機能で使いやすい。ファミリー層に適した容量のモデルが多い。
- おすすめ対象: コスパを重視しつつ、使い勝手の良さも求める人向け。
- 2万円以上のモデル
- 特徴: 高性能でデザイン性が高いモデルが多い。多用途に使えるため、料理の幅が広がる。
- おすすめ対象: 家庭での料理をしっかり楽しみたい人や、高機能モデルを求める人向け。
コスパの良いモデルを選ぶポイント
- 使用頻度を考慮する
価格が高くても、頻繁に使用するなら十分に元が取れます。逆に、あまり使わないなら安価なモデルが無難です。 - 必要な機能に絞る
自分に必要な機能を明確にして、それに合ったモデルを選ぶことで、余計な出費を抑えられます。
価格帯をしっかり比較し、自分の予算と用途に合ったモデルを選ぶことで、満足度の高い買い物ができます。
COSORIは性能と価格のバランスが良く、コスパの高い選択肢だと感じています!
保証やアフターサポートの充実度
最後に重要なのが、保証やアフターサポートの内容です。
長く使う家電だからこそ、購入後のサポートがしっかりしているブランドを選ぶことが安心につながります。
確認すべきポイント
- 保証期間
一般的には1〜2年の保証がついていますが、ブランドによって差があります。COSORIは2年保証がついているため、安心して使えます。 - 交換や修理の対応
故障時にどの程度の対応が受けられるかを事前に確認しておきましょう。 - 問い合わせ対応の速さ
カスタマーサポートの対応が早いかどうかは口コミや公式サイトで調べておくと良いです。
保証やサポートが充実しているブランドを選ぶことで、長く安心して使える製品を手に入れられます。
COSORIは購入後のサポートが丁寧で、万が一の時にも安心できる点が魅力的です!
ノンフライヤーのメリットとデメリットを徹底解説

メリット①:油を使わずヘルシーに調理
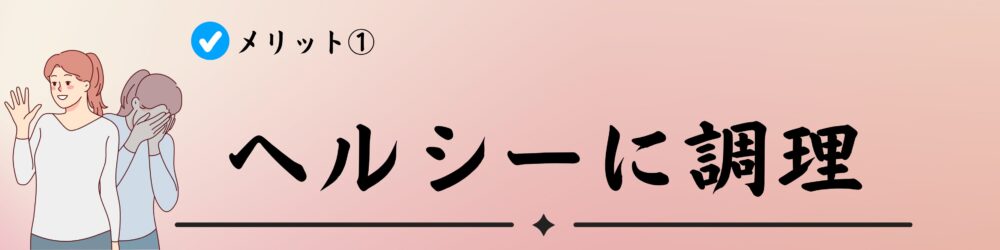
ノンフライヤーの最大の魅力は、油をほとんど使わずに揚げ物が楽しめることです。
私がCOSORIのノンフライヤーを使い始めた理由の一つも、「揚げ物は好きだけど、油の摂取量が気になる」という健康志向でした。
ヘルシー調理のポイント
実際の仕上がり
COSORIのノンフライヤーで作った唐揚げやフライドポテトは、外はカリッと中はジューシー。もちろん油を使った揚げ物と全く同じではないですが、十分満足できる味わいです。油を使わずヘルシーに調理できるノンフライヤーは、健康志向の方やダイエット中の方に特におすすめです。私は揚げ物を楽しみつつ、健康管理がしやすくなりました!
メリット②:調理が簡単で初心者にも使いやすい
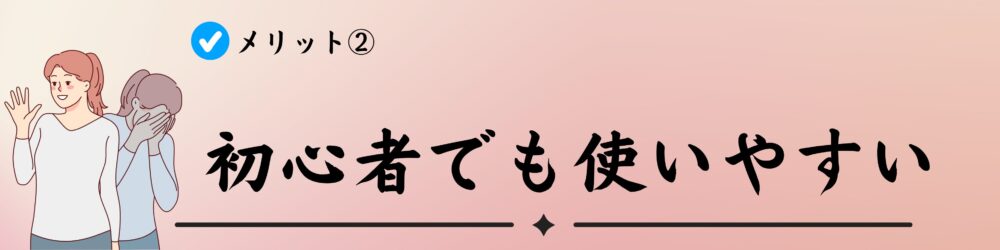
ノンフライヤーを使い始めて驚いたのが、調理の手軽さです。
料理が苦手な方や時間がないときでも、ノンフライヤーなら簡単に美味しい料理が作れます。
使いやすさのポイント
- 材料をセットしてスイッチを押すだけ
食材をトレイに並べて温度と時間を設定するだけで、調理がスタート。COSORIにはプリセット機能が搭載されており、唐揚げやフライドポテトなどの定番料理をボタン一つで作れるのが便利です。 - 火加減の調整が不要
ガスコンロで揚げ物を作るときのように、火力を見ながら調整する必要がありません。調理中は放置できるので、他の作業を並行して行えます。 - 初心者でも失敗しにくい
揚げ物を作る際にありがちな「衣が剥がれる」「火が通りにくい」などの失敗が少なく、料理初心者でもプロっぽい仕上がりになります。
私は忙しい日の夕食準備にノンフライヤーをよく使います。例えば、冷凍の唐揚げをセットしてスイッチを押すだけで、カリッと美味しい仕上がりに。
焼き魚や野菜のローストも簡単に作れるので、一品料理だけでなくサイドメニューにも活躍します。
デメリット①:食材によって仕上がりの差がでる
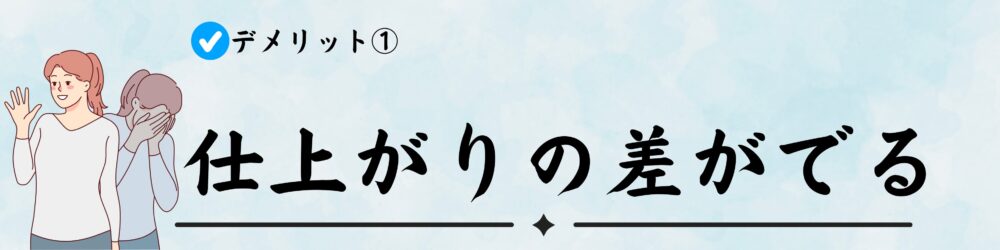
ノンフライヤーにはメリットが多いですが、食材や料理によっては仕上がりに差が出ることもあります。
私が使い始めたときも、食材ごとに調理のコツを掴むのに少し時間がかかりました。
仕上がりの差が出る原因
- 水分量の影響
鶏肉や野菜など水分量の多い食材は、調理中に水分が飛びすぎることがあり、仕上がりがパサつく場合があります。これを防ぐには、オイルを少量スプレーするとしっとり仕上がります。 - 冷凍食品と生の食材の違い
冷凍食品はあらかじめ調理がされていることが多いため、ノンフライヤーでも均一に火が通りやすいです。一方で、生の食材を使う場合は、温度や時間の設定に注意が必要です。
対策方法
- 温度と時間を調整する
説明書どおりに調理するだけでなく、食材に合わせて温度や時間を調整すると失敗が減ります。 - 食材の厚さを均一にする
野菜や肉を切る際、厚みを揃えることで均一に加熱できます。
ノンフライヤーは食材の種類によって仕上がりに差が出ることがありますが、工夫次第で改善可能です。
私も初めは試行錯誤しましたが、今ではどんな食材も美味しく仕上げられるようになりました!
デメリット②:音や匂いが気になる場合がある
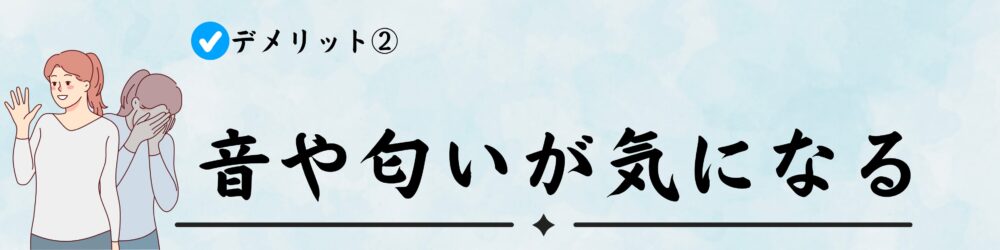
ノンフライヤーを使っていて気になることの一つが、調理中の音や匂いです。
特に、熱風を循環させる仕組み上、音が大きく感じることがあります。
音や匂いに関するポイント
- ファンの動作音
COSORIのノンフライヤーは比較的静音設計ですが、それでもファンが回る「ブーン」という音が調理中ずっと続きます。特に夜間に使うと気になることがあります。 - 食材の匂いが部屋に広がる
揚げ物や焼き魚などの調理では、食材の匂いがキッチンに広がることがあります。油で揚げる場合よりは軽減されますが、完全になくなるわけではありません。
対策方法
- キッチン換気をしっかり行う
調理中は換気扇を強めに回すか、窓を開けて空気の流れを作ることで匂いを軽減できます。 - 音が気になる場合の工夫
ファンの音が気になる場合は、調理時間中に他の部屋で過ごすのも一つの方法です。調理が終わると音はすぐに止まるため、長時間気になるわけではありません。
音や匂いはノンフライヤーを使う上で少し気になる点ですが、事前に対策を講じれば大きな問題にはなりません。
COSORIのモデルは比較的静かで、私自身はほとんど気にならずに使えています!
他の家電(トースターや電子レンジ)との違い
ノンフライヤーはトースターや電子レンジと似た部分もありますが、それぞれに得意分野があります。
ノンフライヤーを購入する際は、これらの家電との違いを理解しておくことが重要です。
主な違い
- トースター
トースターはパンやピザなどの焼き上げに優れていますが、揚げ物の調理には不向きです。一方で、ノンフライヤーは揚げ物や焼き物、ローストなど幅広い料理に対応できます。 - 電子レンジ
電子レンジは温め直しが得意ですが、焼き目やカリッとした仕上がりには向きません。ノンフライヤーの場合は外カリッ中はふっくらという仕上がりにできます。 - ノンフライヤー
揚げ物以外にも焼き魚や野菜のローストなど、健康的な料理が簡単に作れる点が大きな特徴です。
ノンフライヤーは他の家電にはない調理の幅が魅力です。
私も電子レンジやトースターと併用しており、用途によって使い分けています!
ノンフライヤーを最大限活用するためのコツ
ノンフライヤーを最大限に活用するには、正しい使い方と工夫が必要です。
私が使い始めて感じたコツをいくつかご紹介します。
活用のコツ
- 少量の油を活用する
油を完全に使わない場合も良いですが、スプレーで少量吹きかけるだけで仕上がりが格段に良くなります。 - トレイの使い方を工夫する
クッキングシートを敷くことで清掃が楽になるだけでなく、食材が焦げ付きにくくなります。 - 新しいレシピに挑戦する
ノンフライヤー専用のレシピブックやSNSを参考に、揚げ物以外の料理にもどんどん挑戦してみましょう。
ノンフライヤーを正しく使えば、日々の料理がさらに楽しく便利になります。
私もいろいろ試しながら、その可能性を広げています!
【後悔させない!】おすすめのノンフライヤー3選!!
「次にノンフライヤーを買うならどれがいい?」と考えたとき、私が選ぶ視点で厳選した3台をご紹介します!
実際に使いやすいだけでなく、家族みんなで楽しめる大容量モデルから、一人暮らしにぴったりなコンパクトサイズまで、それぞれのライフスタイルに合う1台を選びました。
1. COSORI ノンフライヤー 4.7L 【複数人向け】
おすすめポイント:
- 大容量で家族分の食事を一度に調理!
4.7リットルの容量があり、家族での夕食や友人を招いたホームパーティーでも大活躍!1回でたっぷり作れるので、調理の手間が省けます。 - ヘルシーに揚げ物が楽しめる!
油をほとんど使わず、最大97%のオイルカットが可能。唐揚げやフライドポテトが健康的に仕上がります。 - 簡単操作で初心者にも安心
日本語対応のレシピブック付き!プリセットメニューで温度や時間設定も楽々。料理が苦手な人でも美味しく仕上がります。
こんな人におすすめ:
- 家族みんなでたくさんの料理を楽しみたい人
- ヘルシーな食事を簡単に作りたい人
- 初めてノンフライヤーを使うけど、失敗したくない人
2. Wallfire ノンフライヤー 4.5L 【複数人向け】
おすすめポイント:
- 調理中の様子が見える安心設計!
可視窓付きなので、食材がどんな風に仕上がっているかが一目で分かります。揚げすぎや焼きすぎの失敗を防げます。 - LEDディスプレイ&タッチ操作で簡単便利!
高級感あるデザインと直感的な操作性が魅力。誰でもすぐに使いこなせます。 - 静音設計で使いやすい
音が静かなので、夜でも周りを気にせず調理可能。省エネ設計で電気代も気になりません。
こんな人におすすめ:
- 手軽にプロっぽい料理を作りたい人
- デザイン性の高いキッチン家電が欲しい人
- 操作が簡単でストレスなく使えるノンフライヤーを探している人
3. COSORI ノンフライヤー 2L 【一人暮らし向け】
おすすめポイント:
- コンパクトで一人暮らしにぴったり!
2リットルの容量で場所を取らず、キッチンスペースが限られている方に最適です。 - 省エネ&スピーディ調理
少量調理に最適な省エネ設計。調理時間も短縮され、忙しい日でも手軽に一品作れます。 - 見た目もおしゃれで機能的!
洗練されたデザインがキッチンを彩り、インテリアにも馴染む高級感があります。
こんな人におすすめ:
- 一人暮らしや少人数で暮らしている人
- ヘルシー志向で手軽に料理を楽しみたい人
- キッチンが狭くても収納に困らないサイズを探している人
ノンフライヤーを使うべき人・使わない方が良い人

ノンフライヤーが向いている人の特徴

ノンフライヤーは、健康的な食生活を送りたい人や、時短調理を重視する人に特におすすめの家電です。
私もCOSORIのノンフライヤーを使い始めてから、「これは自分にぴったりだな」と実感する場面が多くありました。
こんな人にはノンフライヤーがおすすめ!
- ヘルシー志向の人
油をほとんど使わないため、揚げ物を健康的に楽しみたい方にぴったりです。摂取カロリーを抑えられるので、ダイエット中の方や健康に気を使う方には特におすすめです。 - 揚げ物が好きな人
家で揚げ物を作ると油の後片付けが大変ですが、ノンフライヤーならその心配は不要です。鶏の唐揚げやフライドポテトなどが手軽に作れます。 - 忙しくても美味しい料理を作りたい人
温度と時間をセットするだけで放置調理ができるので、忙しい日でも簡単に一品作れます。私も仕事が忙しい日は、ノンフライヤーに任せてその間に他の作業をしています。 - 料理が苦手な人や初心者
火加減の調整や揚げ物特有の失敗がなく、簡単に美味しい料理が作れるのが魅力です。 - 掃除や片付けを簡単に済ませたい人
揚げ物の後の油処理やコンロの掃除がいらないため、後片付けが大幅に楽になります。
私自身、健康を意識して揚げ物を控えていましたが、ノンフライヤーを導入してからはヘルシーな唐揚げを頻繁に作るようになりました。
また、放置調理のおかげで料理の時間が短縮され、毎日の生活が少し楽になったと感じています。
ノンフライヤーが向かない人の特徴

一方で、ノンフライヤーが全ての人にとって完璧な家電というわけではありません。
購入を検討している方は、自分のライフスタイルや調理スタイルに本当に合っているかを見極めることが重要です。
こんな人には向いていないかも?
- 揚げ物のクオリティを最優先する人
油で揚げた本格的なカリッと感や香ばしさを求める場合、ノンフライヤーの仕上がりに満足できない可能性があります。ただし、少量の油を使う工夫をすれば、仕上がりを改善できます。 - 使用頻度が低い人
日常的に揚げ物や焼き物を作らない方にとっては、ノンフライヤーを使う機会が少なくなり、コスパが悪く感じる可能性があります。 - 調理に時間をかけるのが苦でない人
料理を一から丁寧に作るのが好きな人にとって、ノンフライヤーの「簡単すぎる調理」は物足りなく感じる場合があります。
注意点
- 向かない場合でも、活用方法を工夫することで十分満足できる場合もあります。例えば、揚げ物以外の料理や温め直しに使うことで、購入の価値を感じやすくなります。
ノンフライヤーは、生活スタイルや調理スタイルに合わない場合にはその魅力を十分に発揮できないこともあります。
自分の用途に合っているかをじっくり考えてから購入を検討しましょう。
ノンフライヤーの使い方次第で得られる満足感
ノンフライヤーの魅力は、使い方次第でどれだけ便利で満足度の高い調理ができるかにあります。
私も使い始めてから、揚げ物以外にもさまざまな料理に挑戦することで、その可能性を広げています。
ノンフライヤーを最大限に活用する方法
- 揚げ物以外の調理に挑戦する
ローストチキンや焼き魚、グラタン、さらには焼き芋まで、ノンフライヤーで作れる料理は多岐にわたります。私は特にロースト野菜が簡単で美味しく仕上がるのがお気に入りです。 - 冷凍食品の調理に活用する
唐揚げやフライドポテトなどの冷凍食品は、ノンフライヤーで調理するだけで揚げたてのような美味しさを再現できます。 - ヘルシーな調理を楽しむ
油を使わずに調理できるため、ダイエット中の方や健康的な食事を心がけている方にはぴったりです。特に、油をカットするだけでなく、食材そのものの風味を楽しめるのが魅力です。 - 時短調理で生活を快適にする
温度と時間を設定して放置できるため、調理中に他の作業ができるのが便利です。私は夕食を作る間に他の家事を進められるので、時間を有効に使えています。
満足感を高める工夫
- レシピを増やす
COSORIには専用のレシピブックが付属しているので、これを活用して新しい料理に挑戦すると満足感が増します。また、SNSや動画サイトでも多くのレシピが公開されています。 - 家族と一緒に楽しむ
子供と一緒にフライドポテトを作ったり、家族みんなで新しいレシピを試すのも楽しい体験になります。
ノンフライヤーは、使い方次第で満足感を大きく高めることができます。
私も日々の食事作りに取り入れることで、料理がさらに楽しくなりました。
購入を迷っている方も、自分なりの使い方を見つければ、その便利さを実感できるはずです!
まとめ
この記事では、ノンフライヤーを購入する際に後悔しないためのポイントや、実際に使って感じたメリット・デメリットを詳しくお伝えしました。
COSORIのノンフライヤーを使っている私の実体験を交えながら、購入前に知っておきたい注意点や活用方法もご紹介しました。
本記事の重要ポイント
- 後悔する理由とその対策を解説し、購入後の失敗を防ぐ方法を紹介。
- サイズや機能の選び方など、目的別に適したモデルを選ぶポイントを解説。
- ノンフライヤーが向いている人・向かない人の特徴を具体的に説明。
- 油を使わないヘルシー調理や放置調理など、メリットを活かした活用術を提案。
- 清掃のコツやサイズ問題の解決策など、実際に使う際の工夫を共有。
ノンフライヤーは、使い方次第で生活をより便利に、そして健康的にしてくれる家電です。
今回の記事が、あなたの購入判断に役立てば幸いです!
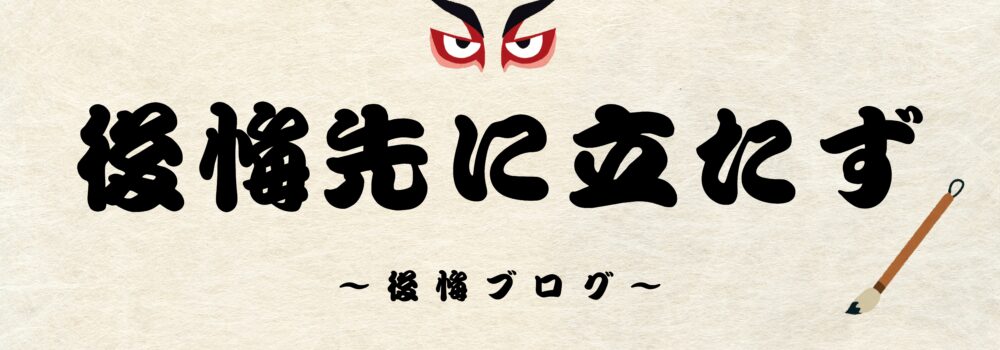
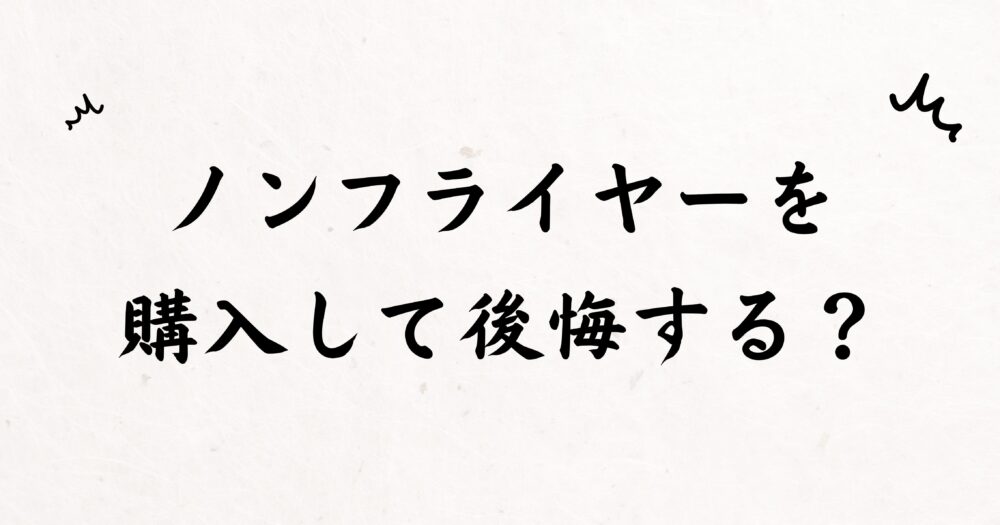






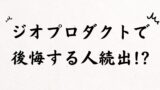
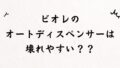
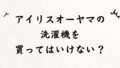
コメント